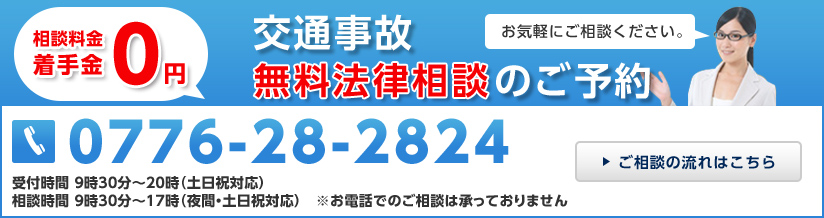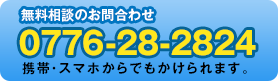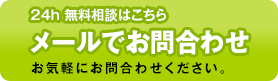非接触事故とは?怪我なしで損害賠償は請求できる?
2025年11月10日

交通事故というと、車やバイクが衝突して発生するものというイメージが一般的です。
しかし、実際には接触がなくても交通事故として扱われるケースがあります。
非接触事故で目立った怪我がない場合、「補償されないのでは?」と不安に思う人もいるでしょう。
今回の記事では、非接触事故の損害賠償請求や事故発生時の対応方法などについて詳しく解説します。
非接触事故に遭い対応で悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてください。
非接触事故で怪我なしでも損害賠償は請求できる?

怪我がなくても、非接触事故によって発生した損害については損害賠償を請求できる可能性があります。
ただし、怪我がない場合は請求できる損害の範囲が限られるため、何が補償対象になるかを理解することが重要です。
・そもそも非接触事故とは?
・非接触事故で請求できる可能性のある損害賠償項目
以下では、非接触事故の概要や事故に遭った際に請求できる損害賠償項目について解説していきます。
そもそも非接触事故とは?
非接触事故とは、物理的に接触していないにもかかわらず、加害者の行動が原因で被害者に損害が発生した事故です。
たとえば、無理な車線変更や急な割り込みがあり、接触を避けようとした結果ガードレールに衝突するなどの状況が該当します。
非接触事故は損害が補償されないと思われがちですが、加害者の過失が証明できれば損害賠償請求が可能です。
しかし、実際の接触がないことから、加害者の行為と事故による損害の因果関係が争点となりやすい特徴があります。
非接触事故で請求できる可能性のある損害賠償項目
非接触事故でも、加害者の過失や事故と損害の因果関係を証明できれば損害賠償を請求できます。
請求できる可能性のある主な損害賠償項目は、以下のとおりです。
・治療費
・通院交通費
・休業損害
・逸失利益
・自動車の修理費用
・代車使用料
・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料
事故の状況や被害の程度によって、請求できる項目が異なります。
非接触事故でまったく怪我をしていない場合は、修理費用や代車費用など物損に関する賠償しか認められません。
しかし、痛みやしびれなどがない場合でも怪我をしている可能性はあるため、事故後は必ず医療機関で診察を受けておきましょう。
非接触事故が発生したときの対応の流れ

非接触事故が発生した場合は、以下のような流れで対応を進めます。
・加害者に事故が発生したことを伝える
・警察に報告する
・自覚症状がなくても病院で検査を受ける
・示談交渉を進める
事故直後の対応によって、後々の損害賠償請求に大きく影響する可能性があるため注意が必要です。
以下では、それぞれの工程について詳しく確認していきましょう。
加害者に事故が発生したことを伝える
非接触事故では加害者が事故に気づいていないケースもあるため、まずは事故が起きた事実を相手にしっかりと伝えましょう。
可能であれば、住所・氏名・連絡先・保険情報など加害者に関する情報を確認しておくことも重要です。
ただし、非接触事故では加害者が事故現場を離れてしまうケースも多いでしょう。
加害者が立ち去った場合には、加害車両の車種やナンバー・事故現場・被害状況などの証拠をできるだけ多く集めることが有効です。
警察に報告する
非接触事故であっても、警察への通報は必須です。
交通事故として正式に扱われるためには、警察に「交通事故証明書」を発行してもらう必要があります。
交通事故証明書がなければ、保険金や損害賠償金の請求の根拠を適切に主張できなくなる可能性があります。
また、加害者が事故と認めていない場合でも、警察に状況を説明しておくことで、後のトラブルを避けやすくなります。
警察が到着した後の実況見分や事情聴取には、できる限り協力するようにしましょう。
自覚症状がなくても病院で検査を受ける
怪我をしていないように思えても、事故後はできるだけ早く病院で検査を受けましょう。
交通事故によるむち打ちや打撲などは、事故直後には自覚症状がないケースも珍しくありません。
後日になって痛みや違和感が出た場合、事故との因果関係を証明するためには「事故直後の受診」が重要になります。
診断書があれば損害賠償請求の根拠にもなるため、早めに受診して記録を残しておきましょう。
示談交渉を進める
治療が完了した後は、加害者との間で損害賠償に関する示談交渉を行います。
交渉では感情的にならず、冷静かつ根拠にもとづいた主張を行うことが大切です。
しかし、非接触事故の場合は加害者の過失や賠償の範囲について争いになりやすく、交渉が難航するケースもあるでしょう。
示談交渉や損害賠償請求の過程で不安があれば、弁護士への相談をおすすめします。
怪我あり・なしにかかわらず非接触事故に遭ったら弁護士への相談がおすすめ

非接触事故に遭った場合は、怪我の有無にかかわらず、早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に相談する主なメリットは、次の3つです。
・事故の証拠集めをサポートしてもらえる
・相手方との交渉を任せられる
・適切な過失割合や損害賠償金を判断できる
それぞれのポイントについて、以下で具体的に解説していきます。
事故の証拠集めをサポートしてもらえる
弁護士に相談・依頼すると、手間のかかる証拠集めをサポートしてもらえます。
非接触事故では加害者との直接の接触がないため、事故の事実や被害状況を証明する証拠の確保が非常に重要です。
事故状況にあわせて、ドライブレコーダーの映像・防犯カメラの記録・目撃者の証言などを迅速かつ的確に収集する必要があります。
しかし、個人で集められる証拠には限界があり、被害者だけでは事故の証明が困難なケースもあるでしょう。
弁護士に相談すれば、どのような証拠が必要かを具体的にアドバイスしてもらえるほか、証拠の収集をサポートしてもらえます。
相手方との交渉を任せられる
弁護士は示談交渉の代行が可能なため、事故の相手方とのやり取りを任せられます。
示談交渉では、法律や過失割合の知識が求められるケースも多く、個人で対応するのは大きな負担になりがちです。
専門用語や制度に関する理解の不足によって、不利な条件で示談が成立してしまうリスクもあります。
弁護士に依頼すれば、これらの交渉をすべて代行してもらえるため、安心して手続きを進められるでしょう。
とくに加害者が過失を否定しているケースでは、専門家である弁護士の介入が効果的です。
適切な過失割合や損害賠償金を判断できる
弁護士は、法的な観点から適切な過失割合や損害賠償金を判断できます。
過失割合とは、事故の加害者と被害者にそれぞれどの程度の過失(責任)があるかを割合で示したものです。
交通事故では、過失割合が損害賠償の金額に大きく影響します。
しかし、過失割合を適正に判断するには交通事故の事例や裁判例を参考にする必要があるため、個人での判断は困難です。
弁護士であれば、これまでの事例や法律にもとづいて、適正な過失割合や損害賠償額を導き出せます。
また、必要に応じて主張・立証も行ってくれるため、被害者にとって納得のいく結果を得やすくなるでしょう。
非接触事故に遭ったときは早めに弁護士に相談しよう

非接触事故であっても、損害を被った場合は加害者に対して損害賠償の請求が可能です。
しかし、損害賠償請求を行うには、加害者の過失と事故との因果関係を証明する必要があります。
初期対応を誤ると、十分な補償を受けられない可能性もあるため注意が必要です。
加害者との認識の差や保険会社とのやり取りに不安がある場合は、早い段階での弁護士への相談をおすすめします。
「軽微な事故」と自己判断せず、弁護士のサポートを活用して適切な補償を受けましょう。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。