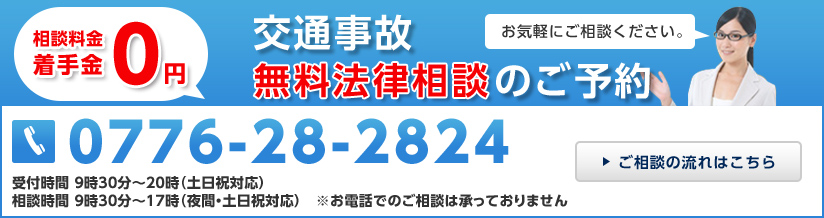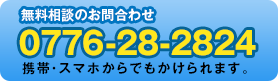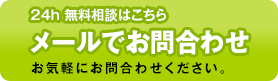社用車で交通事故が起きた場合、責任の所在は?
2025年05月12日

社用車の運転中に交通事故を起こしてしまった際、誰の責任となるのか、またどのように対応すべきか迷うケースは多いでしょう。
社用車での交通事故は、運転者本人だけでなく会社にも責任が及ぶ可能性があります。
今回の記事では、社用車における事故の責任の所在や費用負担、対応手順などについて詳しく解説します。
万が一のトラブルに備え、正しい知識を持っておくことが重要です。
社用車運転中に交通事故が起きたときの責任は?

社用車の運転中に交通事故を起こした場合、事故の当事者となる運転者本人は当然責任を負います。
また、会社側も責任を負うことになる可能性が高いです。
・運転者は事故当事者として責任を負う
・会社は使用者責任と運行供用者責任を負う
以下では、それぞれの立場からの責任について詳しく見ていきましょう。
運転者は事故当事者として責任を負う
社用車で交通事故を起こした運転者には、通常の交通事故と同様に法律上の3つの責任が生じます。
具体的には、「民事責任」「刑事責任」「行政責任」の3種類です。
| 責任の種類 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 民事責任 | 被害者が受けた損害を賠償する責任 | 治療費や修理費・慰謝料などの支払い |
| 刑事責任 | 法律違反の罰を受ける責任 | 過失運転致死傷罪などによる刑事罰 |
| 行政責任 | 行政処分を受ける責任 | 免許停止・取消、違反点数の加算 |
これらの責任の重さは、交通事故の内容や過失の程度によって異なります。
重大事故を起こした場合などでは、複数の重い責任を同時に問われるケースもあるでしょう。
会社は使用者責任と運行供用者責任を負う
従業員が業務中に社用車で事故を起こした場合、会社側も責任を負うことになります。
問われる可能性のある責任は「使用者責任」と「運行供用者責任」の2種類です。
使用者責任とは、従業員が第三者に損害を与えた場合に、会社も連帯責任として賠償責任を負う制度です。
使用者は従業員の活動によって利益を得ているため、その活動で第三者に損害が生じた際は賠償責任を負うべきとされています。
一方で運行供用者責任とは、自動車の運行によって他者の生命や身体を害した場合に、運行供用者が負う賠償責任です。
運行供用者とは、自動車の運行を管理・支配し利益を得る者であり、社用車の場合は会社が運行供用者となります。
どの責任が生じるかは、業務時間内・時間外のどちらで起きた事故か、また自動車が誰の名義かなどによって異なります。
【自己負担・会社負担】社用車の交通事故で支払う費用

社用車の運転中に交通事故が発生した際、支払うべき主な費用の項目は以下のとおりです。
・従業員の治療費
・事故相手に対する損害賠償金
・社用車の修理費用
これらの費用に関して、従業員が自己負担すべきか、会社が負担すべきか判断に悩むケースもあるでしょう。
以下では、費用項目ごとの扱いについて解説していきます。
従業員の治療費
社用車の事故で従業員が負傷した場合、その治療費は原則として労災保険から支給されます。
業務中の事故は業務災害、通勤中の事故は通勤災害として扱われるため、治療費を自己負担する必要はありません。
ただし、通勤途中で寄り道をしていたときや、プライベートな用事での事故は労災保険の対象外となる可能性があります。
労災保険が適用できるか、また会社に請求できるかどうかは事故状況によって異なるため、事実確認や会社側との交渉が必要です。
事故相手に対する損害賠償金
事故相手から損害賠償金を請求された際は、基本的に従業員と会社の連帯責任となります。
社用車での交通事故は、従業員と会社双方に責任が発生するためです。
したがって、事故の被害者は従業員と会社どちらに対しても損害賠償請求ができることになります。
損害賠償金として請求される可能性があるのは、主に以下のような項目です。
・治療関係費
・慰謝料
・修理費
・休業損害
・逸失利益
実際に請求される項目や金額は、損害の程度によって大きく異なります。
社用車の修理費用
交通事故によって社用車が損傷した場合、その修理費用は原則として会社が負担します。
社用車は会社の所有物であり、車両の管理責任は会社にあるためです。
事故を起こしたのが従業員であったとしても、社用車の修理費用を従業員に請求するケースは少ないでしょう。
ただし、従業員側に重大な過失や規則違反があった場合、修理費用を請求される可能性はあります。
社用車で交通事故を起こした際の対応の流れ

社用車で交通事故を起こした際の基本的な対応の流れは、以下のとおりです。
・ケガ人の救護と安全確保を行う
・警察に連絡する
・会社に連絡する
・事故状況を確認し記録する
・自身もケガをした場合は病院を受診する
適切な対応を取らないと、後のトラブルや責任問題に発展する可能性があるため注意しましょう。
事故発生直後から取るべき対応について、以下で順に解説していきます。
ケガ人の救護と安全確保を行う
交通事故が発生した際、まず最優先すべきなのは人命救助です。
事故による負傷者がいる場合は意識の確認や応急処置を行い、救急車を呼びましょう。
負傷者に気づかなかったり、軽傷だからといった理由で立ち去ったりした場合、ひき逃げとして罰せられる可能性があります。
また、事故現場が車両の往来が多い場所であれば、二次災害を防ぐためにも発煙筒などを活用して安全確保に努めます。
道路の中央での停車や不用意な移動は避け、周囲の安全を十分に確認しましょう。
警察に連絡する
交通事故を起こしたら、警察に通報する必要があります。
警察に交通事故があった事実を報告することは、道路交通法で定められた運転者の義務です。
負傷者のいない物損事故であったとしても、報告をしなければ報告義務違反として罰せられる可能性があります。
また、警察の現場検証を受けなければ「交通事故証明書」が発行されません。
交通事故証明書は保険金の請求や会社への報告に必要となるため、必ず現場で警察の到着を待ちましょう。
会社に連絡する
負傷者の救護や安全確保・警察への連絡などが済み事故後の対応が落ち着いたら、会社に連絡します。
社用車の事故の場合、保険契約の確認や今後の対応を会社側で判断する必要があるためです。
通常であれば、自賠責保険に加えて対人賠償責任保険や車両保険といった任意保険に加入しているケースが多いでしょう。
任意保険が利用できる状況であれば、負傷者の治療費や社用車の修理費用は保険でカバーできます。
スムーズに手続きを進めるためには、できるだけ早めの連絡が重要です。
事故状況を確認し記録する
事故が発生した際は、可能な範囲で事故状況を確認し記録しておきましょう。
具体的には、以下のような情報を記録しておくのがおすすめです。
・事故発生時の時間・場所・天候・道路状況・スピード
・事故現場の位置関係
・車両の損傷の程度
・ドライブレコーダーの映像
・負傷者の有無と状況
・事故後の対応
これらの情報を写真やメモで残しておくと事故状況の証拠になり、警察や会社・保険会社への説明にも役立ちます。
記録を取る際は無理をせず、安全な場所から行いましょう。
自身もケガをした場合は病院を受診する
事故によって自身もケガをした場合は、速やかに病院を受診しましょう。
事故後すぐはアドレナリンの影響で痛みを感じにくく、後から症状が出るケースがあります。
自覚症状がなかったとしても、念のため病院で診察を受けておくことが望ましいです。
必要な診断や検査を受けたら診断書を取得しておくと、労災申請や保険請求に活用できます。
社用車の交通事故に関するトラブルは弁護士に相談しよう

社用車の事故では、責任の所在や損害賠償・治療費の請求など、複雑な問題に直面する可能性があります。
自己判断で対応を進めると、不利な立場に立たされるおそれもあるため、早期に専門家である弁護士への相談を検討しましょう。
弁護士に依頼すれば、会社との交渉や訴訟に発展した場合の対応まで総合的にサポートしてもらえます。
当事務所のWEBサイトをご覧いただきありがとうございます。福井県内での移動は、車での移動が当たり前の「車社会」になっています。ただし、その反動として、福井において、不幸にして交通事故に遭われてしまう方が多数いることも事実です。しかしながら、福井県民の中で、交通事故の被害に遭ったときに弁護士の相談するという発想自体がないこと、弁護士が入れば適正な賠償金額を得ることが出来るということ等を知らない人が多いと実感しています。もし、皆様の周囲で交通事故被害に遭い、お悩みになられている方がいらっしゃいましたら、まずはお気軽にご相談下さい。